第30回 ゆうの森の「心臓部」とは?〜理念の浸透とたんぽぽ方式〜
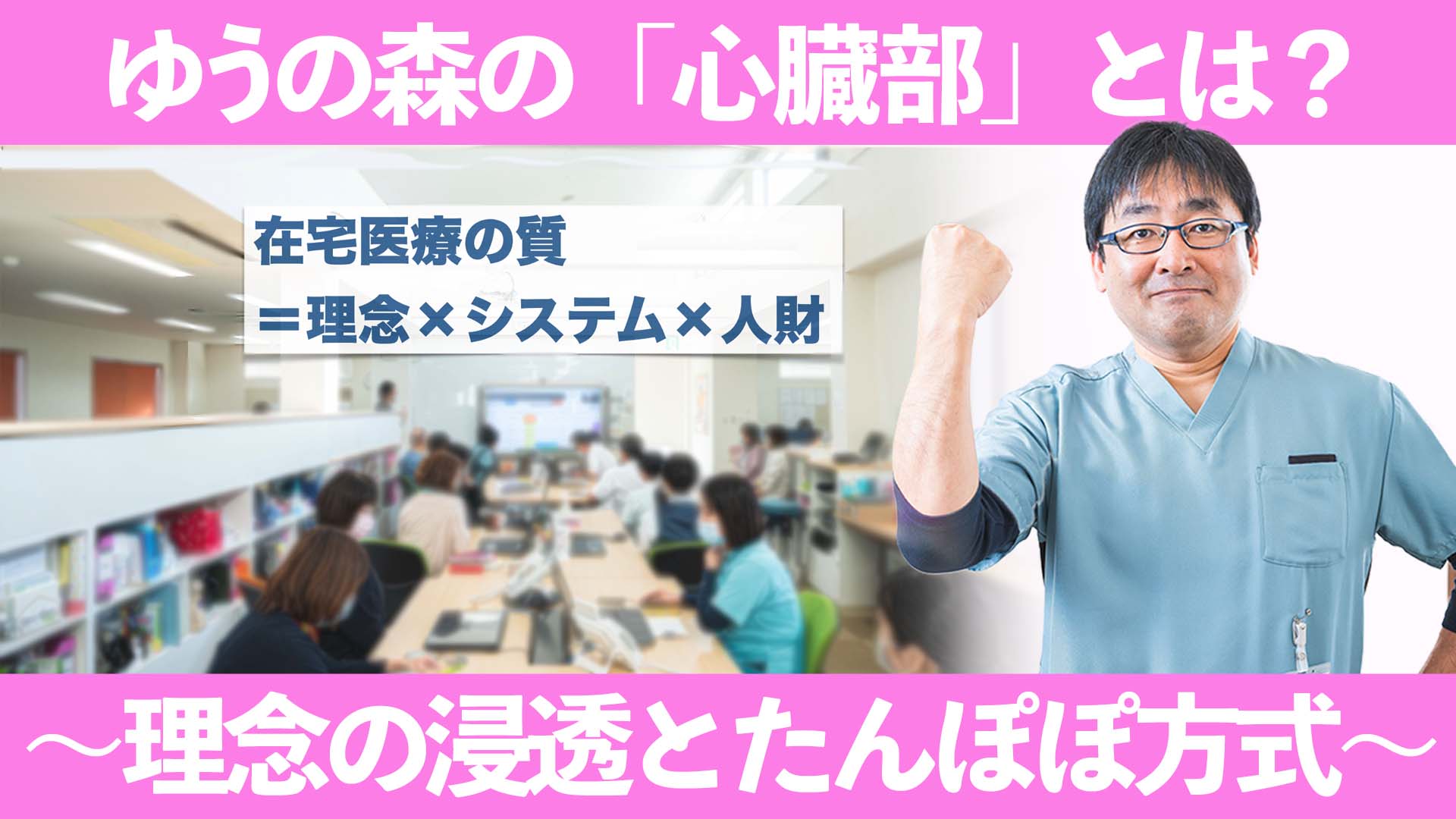
今回は、私たちの法人の「心臓部」ともいえる部分について、お話ししたいと思います。
高い理念を掲げることは大切ですが、それを日々の現場でどう実践していくのか。そして、スタッフが疲れ果ててしまわないように、どんな仕組みを作っているのか。
これが今回のテーマです。
(1) 毎朝のミーティングは「戦略タイム」
一日の始まりは全員集合のミーティング
私たちの一日は、毎朝8時30分の全体ミーティングから始まります。
「おはようございます!」 「今日も1日笑顔で、よろしくお願いします!」
この挨拶の声が、法人全体に響き渡ります。
医師、看護師はもちろん、ケアマネジャー、リハビリスタッフ、管理栄養士、そして事務職員まで。すべての職種のスタッフがミーティングフロアに集まります。
そして面白いのが、松山市の本院から75キロも離れた俵津診療所のスタッフも、テレビ会議で参加してくれていることです。距離を超えて、みんなで一つのチームを作っているのです。
なぜこんなに徹底するの?
「たんぽぽ先生、なんでここまで徹底するんですか?」
よく聞かれる質問です。答えは簡単。
この時間は、単なる申し送りではありません。私たちの法人の「戦略タイム」だからです。
在宅医療は、24時間365日対応です。夜中に当番の先生が患者さんのお家に伺うことがあります。その時に、担当医と違う方針で診療をしてしまったら、患者さんを不安にさせてしまいますよね。
だからこそ、この場で患者さんの情報、治療方針、ケアの方向性を、とことん共有するのです。
白熱する議論
特にターミナル期の患者さんについては、真剣に話し合います。
「告知は十分にできているのか」 「残された時間をどう過ごしたいと思っていらっしゃるのか」 「そのために私たちは何をすべきなのか」
こういったことを、多職種でとことん議論するのです。
時には議論が白熱して、1時間を超えることも珍しくありません。でも、これがとても大切な時間なのです。
(2) 連携は「無力さ」の自覚から
医療職以外も参加する意味
「なんで医療職以外のスタッフも参加するんですか?」
これもよく聞かれる質問です。
実は、すごく大きな意味があるのです。
事務職員の方でも、一人の患者さんへの取り組みを知ることで、「自分たちの組織がどこを目指しているのか」「自分の仕事がどう繋がっているのか」を実感できるようになるのです。
「無力さ」の自覚が連携の出発点
在宅医療は、医療だけでは絶対に成り立ちません。
訪問診療や訪問看護、私たちだけのサービスでは、患者さんの1日の大半の生活を支えることは不可能です。
「自分たちだけでは、患者さんの人生は支えられない」
この、ある種の"無力さ"を自覚するところから、本当の多職種連携が始まるのです。
この毎朝のミーティングは、職種を超えて「チームとして患者さんを支える」という意識を作る、最も重要な時間です。
(3)「たんぽぽ方式」で疲弊しない仕組み
スーパーマンは要らない
高い志を持つ人ほど、自分を犠牲にしてでも患者さんのために頑張ろうとします。
でも、ちょっと待ってください。
自分の人生や生活を犠牲にして行う医療は、その人がいなくなったら続けられません。
「たんぽぽ方式」という24時間システム
そこで私たちが作ったのが、「たんぽぽ方式」という24時間対応システムです。
これは、医師や看護師といった同じ職種のスタッフが、最低でも4人以上で当番を組む「4人1ユニット制」が基本です。
例えば医師の場合、4人いれば、
・平日の夜間対応:週に1回
・週末の対応(金曜夜から月曜朝):月に1回
これで済むのです。当番の日以外は、しっかり休むことができます。
オンとオフをはっきりさせるために
この「オン」と「オフ」をはっきりさせるためには、当番でない日に、自分の患者さんを他のスタッフに安心して任せられる信頼関係が絶対に必要です。
だからこそ、毎朝のミーティングでの「情報の共有」と「方針の統一」が、絶対的な鍵になるのです。
理念だけを振りかざすのではなく、それを支える具体的なシステムがあって初めて、組織は永続的に質の高い医療を提供し続けられるのです。
(4) 質の高い在宅医療の方程式
方程式で表す在宅医療の質
私は、在宅医療の質を、次の方程式で表せると考えています。
『在宅医療の質 = 理念 × システム × 人財』
目指すべき目標である「理念」 それを動かすエンジンである「システム」 そして実際に操縦する優秀なスタッフである「人財」
この3つの要素が掛け合わさって、初めて質の高い在宅医療が実現します。
掛け算の意味
なぜ掛け算なのか。
どれか一つがゼロであれば、答えはゼロになってしまうからです。
どんなに素晴らしい理念があっても、それを実現するシステムがなければ絵に描いた餅になってしまいます。
どんなに優秀な人がいても、理念がなければ方向性を見失ってしまいます。
私たちは、この3つを常に磨き続けることで、組織として成長してきました。
今回は、私たちの組織運営の核心部分についてお話ししました。
でも、この方程式の最後の要素である「人財」。これは一体どうすれば集まり、育っていくのでしょうか?
これについては、また次回詳しくお話ししたいと思います。